※当記事はPRを含みます。
生成AIスクールおすすめ13選【2025年最新】比較表・料金・選び方
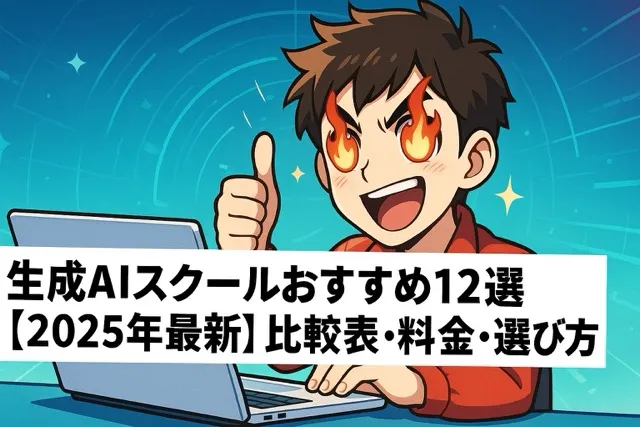
生成AI(ジェネレーティブAI)を効率よく学びたいけれど、「スクールが多すぎてどれを選べばいいかわからない…」と悩んでいませんか?
本記事では、初心者からでも安心して学べるおすすめの生成AIスクール13選を比較し、料金や特徴をわかりやすくまとめました。
 編集長
編集長選び方のポイントや卒業後の活用法、よくある質問への回答も解説するので、ぜひ最後まで読んで自分にピッタリのスクールを見つけてください。
生成AIスクールおすすめ比較一覧表
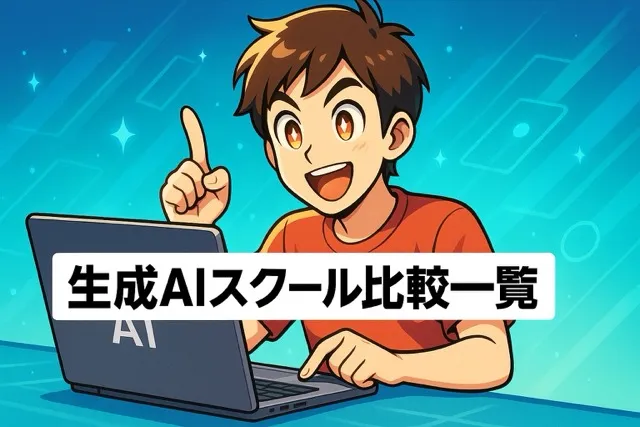
まずは主要な生成AIスクール12社の特徴を比較一覧表で確認しましょう。
| スクール名 | 特徴 | 料金目安 |
|---|---|---|
| デジハク生成AI | 現役プロによるマンツーマンサポートの実践型スクール | 148,000円~ |
| バイテック生成AI | 無期限受講・手厚い質問サポートで副業向け実践スキル習得 | 一括178,000円~ |
| ホリエモンAIスクール | 初心者OK、240以上の講義でAIの基礎から応用まで学べる | 入学金162,800円+月額16,280円 |
| SHIFT AI | 国内最大級のAIコミュニティ。毎日ウェビナー&豊富な講座 | プランにより異なる(無料セミナーあり) |
| キカガク | AI・機械学習に特化した動画学習プラットフォーム | 158,000円~(補助金適用可) |
| DMM 生成AI CAMP | 短期集中の実践カリキュラムと手厚い転職・副業サポート | 198,000円~(最大70%給付金支援) |
| TechAcademy | 完全オンライン。現役エンジニアの指導で基礎から学べる | 149,600円~(4週間プラン) |
| Aidemy | Python実践でAI開発スキル習得。給付金対象コースもあり | 528,000円~(3ヶ月~) |
| 侍エンジニア | 専属マンツーマン指導で柔軟学習。転職成功率業界トップクラス | プランによる(例:4週間165,000円~) |
| RUNTEQ | 9ヶ月・1000時間の徹底カリキュラムでWeb開発基礎からAI活用まで | 550,000円~(給付金で110,000円~) |
| スキルアップAI | AI専門スクール。実務直結の多彩なコースと資格対策あり | コースにより異なる(公式サイト参照) |
| 忍者CODE | 初心者向けオンライン学習。挫折させない工夫で基礎から安心 | 要問い合わせ(リーズナブルな価格設定) |
| デイトラ 生成AIコース | 実践課題中心の自己学習型。低価格で始めやすい | 99,800円(税込) |
生成AIスクールはこんな人におすすめ
生成AIスクールは以下のような人に特におすすめです。
- AIを基礎から体系的に学びたい初心者
- 独学で行き詰まり、サポートが欲しい人
- 仕事や副業に生成AIを活用したい社会人
- 一人の独学が不安で仲間と学びたい人
実務やキャリアアップに活用できるスキルが付く
生成AIスクールで学ぶ最大のメリットは、得たスキルがそのまま実務やキャリアアップに直結することです。
現在、生成AIを自在に扱える人材はまだ少なく(令和6年版情報通信白書によると日本企業の導入率は約9%)、多くの企業で「AIを使いこなせる人」が求められています。
 編集長
編集長スクールで体系的に習得したプロンプト設計やAIツール活用の技術は、業務効率化や新サービス開発など様々な場面で即戦力として活かせるでしょう。
例えば、日常業務の自動化やマーケティング文章の生成をAIで行えれば、一人ひとりの生産性が飛躍的に向上します。
また、生成AIの知識があることで周囲から「AIに詳しい人」として頼られる存在になり、社内で新規プロジェクトを任されたり昇進のチャンスが増えることも期待できます。
副業の面でも、AI文章作成や画像生成のスキルを活かして案件を受注したり、自身でコンテンツを制作して収益化するといった道が開けます。
このように、生成AIスクールで得られるスキルは単なる知識に留まらず、実際の仕事やキャリアに結びつく「価値あるスキル」です。
 編集長
編集長今のうちに身につけておけば、AI活用がさらに広がる将来に向けて大きなアドバンテージとなるでしょう。
なお、AI人材の不足は企業の喫緊の課題であり、こうしたスキルを持つ人には高待遇や重要ポジションが用意されるケースも増えています。今のうちに実務で通用する力を培っておけば、将来のキャリアの選択肢が格段に広がります。
サポートにより継続しやすい環境
独学で挫折しやすい人でも、スクールなら続けやすくなります。
その理由は、メンターや講師によるサポートがあるからです。なお、一般に独学の学習は挫折率が高いと言われますが、スクールでは疑問点を解消しながら進められるため、その点大きく改善されます。
わからない箇所はすぐ質問でき、丁寧に教えてもらえるため、疑問点を抱えたまま先に進んでしまう心配がありません。オンラインチャットやQ&Aフォーラムなど、いつでも相談できる環境が用意されているスクールも多く、孤独を感じずに学習を進められます。
また、定期的な課題提出やメンタリング面談があるスクールでは、適度な締め切りとフィードバックが学習のペースメーカーになります。
自分一人ではついサボってしまう人でも、スクール側から進捗フォローが入ることでモチベーションを保ちやすくなります。
「自分には監視役が必要」という方にとって、手厚いサポート体制のある環境は非常に効果的です。
実際、国内のある調査ではプログラミング独学者の約7割が途中で挫折を経験したと報告されています。スクールではそうした課題を解決し、モチベーションを維持する仕組みが機能していることがわかります。
さらに、他の受講生と切磋琢磨できる点も継続の助けになります。
学習コミュニティ内で成果を共有したり、悩みを相談したりできるため、「自分だけが遅れているのでは」と不安になることもありません。同じ目標を持つ仲間の存在は大きな励みとなり、最後までやり遂げる原動力となるでしょう。
心理面でも、伴走者がいる安心感からモチベーションを高く維持しやすくなります。一人きりの孤独な学習と比べて、スクールの存在は学習者にとって大きな支えとなるでしょう。
現状まだ自己学習が難しい環境
生成AI分野は新しく情報の移り変わりが激しいため、独学で最新知識をキャッチアップするのは容易ではありません。インターネット上には英語資料も多く、初心者が手探りで学ぶにはハードルが高いのが現状です。スクールであれば、体系立てられたカリキュラムに沿って必要な知識を順序良く学べるため、「何から始めればいいのかわからない」という事態を避けられます。
また、信頼できる教材と専門講師による解説があることで、誤った理解をしてしまうリスクも低減できます。独学だと自己流になってしまいがちですが、スクールなら正しい手順で実践的に学べるので、基礎の抜け漏れがありません。
スクールを活用することで、効率よく必要なことを学び、遠回りせずにスキルを身につけることが可能です。市販の書籍や無料動画教材も存在しますが、情報が断片的だったり最新動向を網羅しきれなかったりと限界があります。「結局何から手を付ければいいのかわからない」という壁に突き当たった場合、スクールを賢く利用して効率的に学ぶ選択肢は非常に有効です。
実際、スクール受講者の中には独学で行き詰まり、改めて基礎から学び直してスキルを身につけた方も多くいます。そうした声を聞くと、環境を変えて学ぶ重要性を実感します。効率良く学べる場があるなら、積極的に活用するのが賢明です。
就職サポートやコミュニティなど卒業後にもメリット
生成AIスクールの多くは、受講後のサポート体制も充実しています。
たとえば、転職希望者向けに履歴書の添削や模擬面接、求人紹介といった就職支援を行ってくれるスクールもあります。実際に、スクールを通じてAI分野へ転職を果たしたり、卒業生同士で起業したケースも生まれています。
また、スクール卒業生向けのコミュニティが用意されているケースも珍しくありません。卒業後もそのコミュニティで情報交換を続けたり、新しいAIツールの活用事例を共有し合ったりできます。同じスクールで学んだ仲間という強いつながりがあるため、案件の紹介や共同プロジェクトの立ち上げなど、思わぬビジネスチャンスにつながることもあります。
さらに、卒業後に教材や講義アーカイブへ引き続きアクセスできるスクールもあります。学びっぱなしで終わらず、実際に仕事でAIを使う段階になってからでも必要なときに振り返れるのは、大きな利点です。受講が終わった後も継続してフォローしてもらえるスクールを選べば、長期的な成長においても安心でしょう。
例えば、卒業生向けに毎月勉強会を開催し、最新のAI情報を共有するスクールもあります。在学期間を終えた後も学び続けられる環境があるのは大きな強みです。
このように、スクールは卒業後も“学習コミュニティ”として機能します。得がたいネットワークや継続学習の場を手にできるのは、個人で学習していては得られない大きなメリットです。
学び終えた後も仲間と切磋琢磨し続けられるため、生涯にわたって成長を支えてくれるでしょう。
初心者でも失敗しない生成AIスクールの選び方
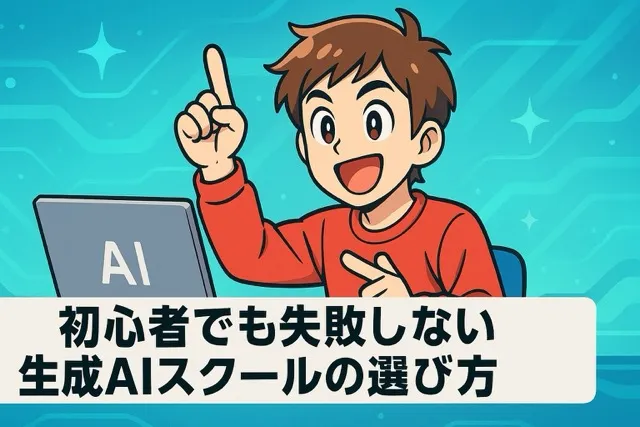
相場に適した価格帯か
スクール選びでは、料金が相場に対して適切かどうかをチェックしましょう。生成AIスクールの受講料は、短期オンライン講座で数万円程度から、本格的な転職支援付きコースで数十万円に達するものまで幅があります。極端に高額な場合は内容と見合っているか要確認ですし、逆に安すぎる場合はサポートが不十分でないか注意が必要です。
費用対効果を見極めるためには、料金に含まれるサービス内容を比較しましょう。マンツーマン指導やキャリア支援があるスクールは相応に費用がかかりますが、その分、得られる成果も大きい傾向にあります。一方、自習中心であまりサポートがない講座であれば、低価格でも妥当と言えるでしょう。
また、国や自治体の補助金制度を活用できるかどうかは、費用面で大きなメリットになります。対象講座なら、受講料の自己負担を最大70~80%抑えられる場合があります。
特に注目したいのが、経済産業省のリスキリング補助金や、厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の2つです。これらの補助金を受けるには、講座契約前の事前申請や、条件をクリアする必要があります。条件を満たす基準は受講講座により異なります。
 編集長
編集長詳しくは各スクールへ確認しましょう。
受講は通学かオンラインか
スクールの受講形式も重要なポイントです。教室に通学する対面型か、自宅で学べるオンライン型か、それぞれメリット・デメリットがあります。
オンライン型は全国どこからでも参加でき、時間の融通が利きやすいのが魅力です。録画講義が提供される場合は、自分のペースで繰り返し学習できる利点もあります。
ただし、自律的に学ぶ姿勢が求められ、生活の中で学習時間をしっかり確保する自己管理が必要です。
一方、通学型(オフライン)は直接講師や他の受講生と顔を合わせて学べるため、臨場感と緊張感があります。わからない点もその場で質問しやすく、モチベーションを維持しやすい人も多いでしょう。
対面のネットワーキングから仕事につながるケースもあります。
ただし、決まった時間に教室へ通う必要があるため、仕事や家庭との両立はオンラインに比べて難しくなることもあります。
現在はオンライン完結のスクールが主流ですが、中にはオフラインのワークショップや交流会を開催してハイブリッド型で学べるスクールもあります。自分の生活スタイルや学習習慣に合わせて、無理なく通える形式を選ぶことが大切です。
生成AIスクールはオンライン学習が基本となるケースが多いため、・インターネットを通じて学習する際に、個人情報や学習データを安全に守ることは大切です。特に公共Wi-Fiや共用ネットワークを使う場合、通信が盗聴されるリスクがあり、こうしたリスクを軽減するためにVPNがおすすめです。
目的にあったコース・学べる内容があるか
スクールによってカリキュラムの内容や得意分野は様々です。自分の学習目的にマッチしたコースを提供しているかを確認しましょう。「AIを使う側」なのか「AIを作る側」なのかによっても適切な講座は異なります。例えば、仕事でChatGPTや生成AIツールを活用したいだけなら、プログラミングをイチから学ぶ必要はなく、プロンプトエンジニアリングやツール活用法に特化したコースで十分でしょう。
一方、「将来的にAI開発者になりたい」「AIの仕組みまで深く理解したい」という場合は、Pythonや機械学習の基礎から教えてくれる総合コースを選ぶ必要があります。
スクールの公式サイトで学べる内容やシラバスを確認し、自分の目標に合ったスキルセットが身につくかを見定めてください。コース名に「応用」や「エンジニア」と付いているものは開発寄り、「活用」や「ビジネス」が付いているものはツール利用寄り、という傾向もあります。
また、初心者なのか経験者なのかによっても選ぶコースは変わります。全くの未経験者なら入門編から始めないと挫折しかねませんし、逆に基礎を押さえている人が入門講座を受けても物足りないでしょう。
多くのスクールはレベル別にコースを用意していますので、自分の現在地に合ったコースを選ぶことが大切です。
相談できるサポート環境は充実しているか(副業支援、転職支援など)
学習中はもちろん、修了後も含めて相談できる体制が整っているかも重要です。わからない点をすぐ質問できるチャットサポートや、定期面談で学習計画を相談できるメンタリングなどのサポート体制が自分に合ったものであるかをチェックしましょう。副業獲得のアドバイスや転職サポートまで行ってくれるスクールであれば、学んだスキルをどう活かすかまで一緒に考えてもらえるので安心です。
特にオンライン学習では、生徒側から積極的に質問しないと放置されてしまうケースもあります。入会前に口コミなどを調べ、「質問に対する回答が遅くないか」「講師が親身に対応してくれるか」といった点をチェックしておくと良いでしょう。公式サイトでサポート内容を売りにしているスクールは、比較的フォロー体制に力を入れていると考えられます。
また、転職支援については、提携企業からの求人紹介や面接対策が含まれているか確認しましょう。副業支援の場合は、実案件を模擬体験できる課題や、受講生コミュニティ内で仕事募集が行われているかなどがポイントです。せっかく習得した生成AIスキルを次のステップにつなげるためにも、サポートが手厚いスクールを選ぶことで「学びっぱなし」で終わらせずに済みます。
AIを使う側か作る側かを決める
前述の通り、生成AIスキルには「AIを使いこなす人」と「AIを開発する人」という大きく2つの方向性があります。自分が目指すのはどちらなのか、最初に決めておくことがスクール選びでは肝心です。
AIを使う側、つまり非エンジニアとして業務効率化やクリエイティブ用途に活かしたい場合、難しいプログラミング知識よりも、各種生成AIツールの使い方やプロンプトの工夫方法を重点的に学べるスクールが適しています。
逆に、AIそのものを作る側になりたい場合、プログラミングやデータサイエンスの基礎から勉強できるコースが必須です。モデルの構築やAIアプリ開発まで視野に入れるなら、Pythonプログラミングや機械学習理論をしっかり教えてくれるスクールを選びましょう。受講期間も長め(6ヶ月以上)の本格コースになる傾向があります。
このように、自身が「AIのユーザー」志向なのか「AIエンジニア」志向なのかで最適な学習内容は変わってきます。
 編集長
編集長途中で方向転換すると遠回りになってしまうため、スクール申し込み前に目標を明確化しておきましょう。
もちろん両方学びたい欲張りな方は、まず使う側のスキルを短期で身につけてから、次のステップで開発側に挑戦するといった段階的な学習計画もおすすめです。
生成AIスクールおすすめランキング13選
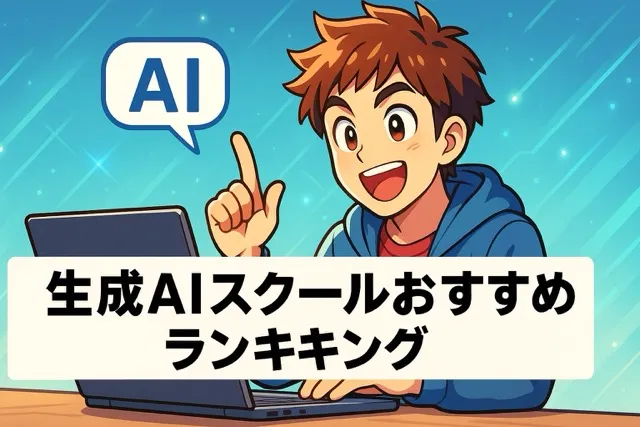
デジハク生成AI

デジハク(生成AIスクールコース)では、未経験者でも「AIを活用して動画・画像・アプリ開発・業務効率化」といった実務レベルの使い方を学べるようカリキュラムが組まれています
学習期間やサポートの有無に応じて 60日プランと 180日プランがあり、後者ではロードマップ設計・定期面談・チャット質問など「伴走型」の支援が受けられます。
特に「生成AI×動画編集」「画像生成」「ノーコードAIアプリ開発」「プロンプトエンジニアリング」といったトピックが盛り込まれており、AIツールの使い方だけでなく“ビジネスとして活用する”視点も含まれているのが特徴です。
ただし料金を投資と捉え、自ら行動に移せるかどうかが成果を左右する点も指摘されており、「受講すれば勝手に稼げる」という期待は避けたほうが良いという評価もあります
バイテック生成AI

バイテック生成AIは、未経験からでも副業や業務に直結するAIスキルを習得できるオンラインスクールです。最大の特徴は、受講期間が無期限であることです。一度受講料を支払えばカリキュラムの閲覧期限がなく、自分のペースでじっくり学習できます。学習コンテンツは動画教材を中心に構成され、その数は300本以上にも及びます。
さらに、質問サポートが1年間ついている点も安心ポイントです。学習中にわからないことがあれば、チャットで気軽に質問して専門スタッフから回答を得られます。実践的な課題も豊富に用意されており、学んだ知識をすぐにアウトプットしながら身につけられるため、ただ動画を見るだけで終わらず実務レベルのスキルが養われます。
料金は一括払いで約18万円~と、手厚いサポート内容を考えると比較的リーズナブルです。受講生満足度は92%と公表されており、サポートの質や教材内容に定評があります。副業案件をこなしたい社会人や、忙しい中でも自分のペースで学習したい方におすすめのスクールです。
ホリエモンAIスクール

ホリエモンAIスクールは、実業家の堀江貴文氏(ホリエモン)と株式会社フェローズが運営するAI特化のオンラインスクールです。240本以上の講義動画が用意されており、AIの基礎から応用、ビジネス活用まで幅広く学べるのが特徴です。プログラミング未経験者でも取り組める内容になっており、専門用語も噛み砕いて説明してくれるため、AI初心者でも安心です。
カリキュラムは自分の興味やレベルに合わせて選択できる柔軟性があります。「とりあえずAIとは何か基礎から知りたい」という方から、「具体的に業務で使えるAIツールのテクニックを学びたい」という方まで、それぞれに合った講義を受講できます。また、受講生同士のコミュニティもあり、質問や情報交換ができる環境が整っています。
料金体系は入学金162,800円(税込)+月額16,280円のサブスクリプション制です。月額制なので、自分のペースで続けられる期間だけ利用できる点は魅力です。堀江氏自らが監修していることもあり、ビジネス視点で実践的なAI活用ノウハウを学べるのも強みです。体系立てて幅広くAIについて学びたい社会人に適したスクールと言えるでしょう。
SHIFT AI

SHIFT AIは、会員数20,000人を超える国内最大級のAI学習コミュニティです。「AI大学」とも称され、生成AIを中心にAI活用スキルを体系的に習得できる場を提供しています。特徴はなんといってもコミュニティの規模と活発さで、ほぼ毎日オンラインウェビナーや勉強会が開催されており、最新のAIトレンドや実践ノウハウを常にキャッチアップできます。
講座数も非常に豊富で、50以上の専門コースと1,000本を超える講義動画が用意されています。ビジネスでのAI活用事例から技術的な内容まで幅広くカバーしているため、自分の興味に合わせて学習コンテンツを選べます。また、受講生同士の交流イベントや数百人規模のオフラインイベントも定期的に開催されており、ネットワーク作りにも最適です。
料金はプランによって異なりますが、まずは無料のオンライン説明会に参加して雰囲気を掴むことが推奨されています。10万人以上が受講した無料セミナーも開催されており、そこでAI時代のキャリアアップ術なども学べます。「日本をAI先進国にする」というミッションを掲げる運営母体だけあり、コンテンツの質と量には定評があります。継続的に最新スキルを身につけたい人や、仲間と切磋琢磨しながら成長したい人にぴったりのコミュニティ型スクールです。
キカガク

キカガクは、AI・機械学習に特化したオンライン動画学習プラットフォームです。1,000社以上の企業研修実績を持つなど信頼性が高く、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応した講座を提供しています。生成AIに限らず、ディープラーニングやデータサイエンスまでカバーしているため、AI分野を総合的に学びたい人に向いています。
カリキュラムは動画視聴と課題演習を組み合わせた構成で、基礎理論から実践への橋渡しが丁寧に行われます。例えば、「生成AIビジネス実践コース」ではビジネス目的でのAI活用事例を学び、「AI人材育成長期コース」では約6ヶ月間かけてAI・データサイエンスの基礎から応用までじっくり習得することが可能です。専門実践教育訓練給付金の対象講座もあり、条件を満たせば受講料の70%程度が戻ってくる制度も利用できます。
最低受講料は約158,000円~(4週間プランの場合)と公表されており、1プランで複数の講座が見放題になる仕組みです。動画学習中心なので自分のペースで進めやすく、忙しい社会人でもスキマ時間で勉強できます。AIエンジニアやデータサイエンティストを目指す方、幅広いAI知識をインプットしたい方におすすめのスクールです。
DMM 生成AI CAMP

DMM 生成AI CAMPは、プログラミングスクール大手のDMM WEBCAMPが提供する生成AIスキル習得コースです。未経験からでも最短でプロンプトエンジニアリングやChatGPTのビジネス活用法を学べる実践重視の短期集中カリキュラムが特徴です。講師陣と運営組織は実績豊富で信頼性が高く、初学者にも分かりやすく指導してくれます。
具体的なコースとして、生成AIの基礎から応用まで60日間で習得するコースなどがあり、期間内に効率よく学べるよう教材と課題が最適化されています。キャリア相談や転職支援も充実しており、習得したスキルをどう業務に活かすか、どんな仕事に就けるかまで含めてサポートを受けられます。長年にわたりエンジニア育成をしてきたDMM WEBCAMPのノウハウが活かされており、学習者のつまずきやすいポイントも踏まえた丁寧なカリキュラム設計になっています。
料金はコースによりますが、専門実践教育訓練給付金の対象となっており、条件を満たせば最大70%の受講料支援が受けられます。通常は20万円台後半~30万円台程の受講料が多いですが、給付金適用後は実質数万円で受講できる計算です。短期間で一気にスキルを身につけたい方、補助金を活用してコスパ良く学びたい方にとって魅力的なスクールでしょう。
TechAcademy(テックアカデミー)

TechAcademy(テックアカデミー)は、オンライン完結型のプログラミングスクールとして知られていますが、生成AI分野の入門コース「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」も開講しています。4週間から受講できる短期集中スタイルで、現役エンジニアのメンターが週2回のマンツーマンメンタリングを行ってくれるのが特徴です。チャットでの質問は無制限で受け付けており、学習中に生じた疑問をすぐに解消できます。
このコースでは、ChatGPTをはじめとする生成AIツールの基本的な使い方から、適切なプロンプトの作成方法、業務への応用アイデアまでを学びます。課題として実際にAIを使って文章や画像を生成する演習もあり、手を動かしながら理解を深められます。また、希望者にはテックアカデミーのキャリアサポート(転職相談)も利用可能で、習得したスキルをどう活かすかについて専門スタッフに相談できるのも安心です。
受講料は社会人の場合4週間プランで149,600円(税込)~と比較的手を出しやすい価格帯です(頻繁に割引キャンペーンも実施)。短期間で効率的に学びたい人や、仕事と両立しながら週末中心に勉強したい人に適しています。テックアカデミー全体としての実績とノウハウがバックボーンにあるため、オンライン学習初心者でも丁寧にサポートしてもらえるでしょう。
Aidemy
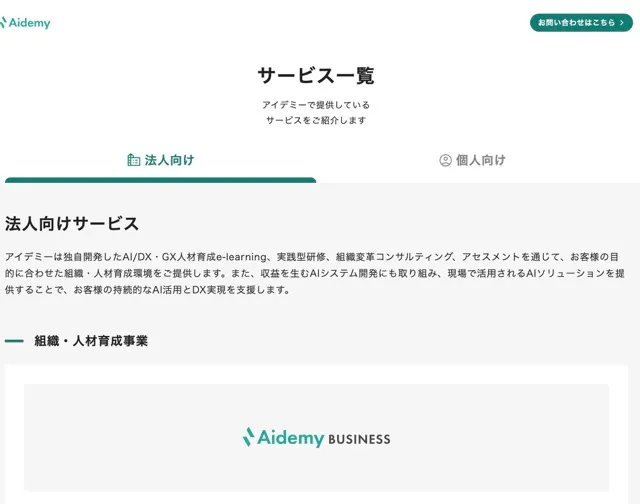
Aidemy(アイデミー)は、AIプログラミング学習サービスとして高い人気を誇るスクールです。中でもAidemy Premiumと呼ばれる有料完結コースでは、生成AIの実践スキルを集中的に学べます。例えば「生成AI活用実践講座」では、ChatGPTを活用したアプリ開発まで視野に入れた包括的なカリキュラムが提供されます。Pythonを用いた基礎文法学習から始まり、API連携による自作AIツール開発、外部サービスとの統合方法など、開発者視点で生成AIを使いこなす内容です。
Aidemyの強みは、ブラウザ上で実際にコードを書きながら学習できるインタラクティブな教材にあります。単に動画を見るだけでなく、自分で手を動かしてコードを書き実行しながら学べるため、知識が定着しやすいです。専属メンターが進捗管理や質問対応をしてくれるため、初心者でも挫折しにくい工夫がされています。課題としてオリジナルAIアプリの作成も行い、ポートフォリオとしてアピールできる成果物を残せるのも魅力です。
受講料は528,000円(税込)~と高額に見えますが、専門実践教育訓練給付金の対象講座となっており、条件を満たせば最大70%(約37万円)の補助を受けることも可能です。本格的にAIエンジニアリングを学びたい人や、開発スキルも含めて市場価値を高めたい社会人に最適です。未経験からでも現場で通用するレベルの実力を身につけられるよう設計されたカリキュラムで、AI業界へのキャリアチェンジを強力に後押ししてくれるでしょう。
侍エンジニア

侍エンジニアは、業界でも珍しいマンツーマン指導型のプログラミングスクールです。生成AI分野でも「業務改善AI活用コース」や「生成AIコース」などを展開しており、受講生一人ひとりの目標に合わせたオーダーメイドカリキュラムで学習を進めます。現役エンジニア講師が付き、学習計画の立案から課題レビューまで伴走してくれるため、挫折率8%以下という高い継続率を誇ります。
侍エンジニアの生成AI関連コースでは、ChatGPTのAPI利用や業務自動化ツールの開発など、受講生の興味やニーズに応じた内容を柔軟に学べます。他スクールのような決まったカリキュラムではなく、「〇〇がしたい」という要望に沿って教材やプロジェクトをカスタマイズしてくれるのが最大の魅力です。例えば、副業でAI記事制作をしたい人には文章生成に特化した課題を、エンジニア志望ならプログラミング演習多めの構成にしてくれます。
費用はマンツーマン指導のため高めですが、その分転職成功率99%※(公式発表)という圧倒的な成果につながっています。短期プランから長期プランまで期間を選べ、スケジュールも柔軟に調整可能です。「自分専用の先生について欲しい」「確実に結果を出したい」という方にはピッタリでしょう。受講後の転職サポートやフリーランス案件紹介も行っており、学んで終わりでなく次のステージにつなげやすい環境です。
RUNTEQ
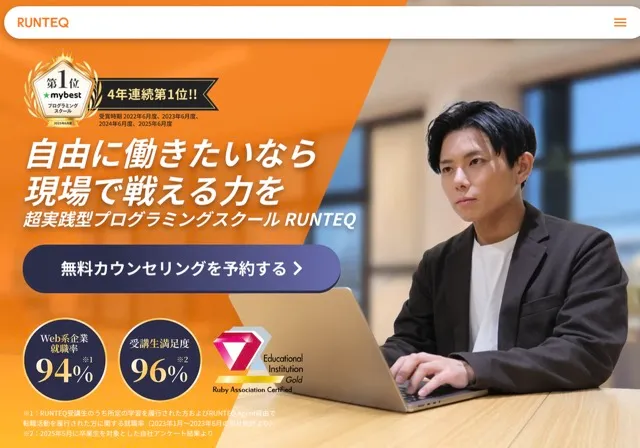
RUNTEQ(ランテック)は、未経験からWebエンジニアへの転職を目指す方向けのオンライン完結型のプログラミングスクールです。一見すると生成AIとは関係ないように思えますが、Web開発スキルとAI活用を組み合わせて学べる点で注目されています。RUNTEQのカリキュラムは非常に実践的で、合計1,000時間に及ぶ演習課題と9ヶ月間の長期トレーニングを通して確かな開発力が身につきます。途中でゲーム感覚のレベルアップ要素も盛り込まれており、楽しみながら継続できる工夫も秀逸です。
生成AIとの関連で言えば、Webアプリ開発の中でChatGPT APIなどを組み込む演習も行われており、「Webサービス×AI」のスキルセットを得られる強みがあります。例えば、自分で作ったWebアプリにAIチャットボット機能を実装してみる、といった発展課題にも対応しています。また、開発基盤となるプログラミングスキル(Ruby on Rails等)を習得しておくことで、将来自社でAI機能を開発したり、AIエンジニアと協業する際にも円滑に対応できる人材を目指せます。
受講料は550,000円(税込)~ですが、給付金利用で110,000円~と大幅に自己負担を減らすことが可能です(専門実践教育訓練の対象)。Web系エンジニア転職率も高く評価されており、AIに限らずITエンジニアとしての総合力をつけたい人に最適です。長期間じっくり学ぶ覚悟がある方には、確かな実力とキャリアを手に入れられるスクールでしょう。
スキルアップAI

スキルアップAIは、AIスキル習得に特化した研修・教育サービスを提供するスクールです。初心者向けの基礎講座から上級者向けのディープラーニング実装講座まで、非常に幅広いコース展開をしています。特徴は、実務で役立つ内容にフォーカスしている点で、講師陣も現場経験豊富なAIエンジニアが揃っています。生成AIに関しても、プロンプトエンジニアリングや画像生成AIの活用講座など、トレンドを押さえた講義を用意しています。
また、日本ディープラーニング協会(JDLA)認定資格(E資格など)の対策コースもあり、単にツールの使い方だけでなくAIに関する理論的な理解を深めたい人にも適しています。オンライン完結のコースが多いですが、一部はライブ配信や対面ワークショップを組み合わせており、双方向の学習も可能です。受講生は自習用の教材をいつでも閲覧できるほか、質問サポートも用意されているため、独学では難しい専門領域も安心して取り組めます。
料金はコースにより様々ですが、例えば短期集中の基礎コースは数万円程度、専門資格対策や長期コースは数十万円規模となっています。公式サイトで詳細な料金表が公開されているので、興味のある分野のコースをチェックしてみるとよいでしょう。「AIを仕事に活かす」を掲げているだけあり、実務直結のスキル習得に重点を置いたスクールです。将来的にAIエンジニアを目指す方から、現職でAIプロジェクトを任されたビジネスパーソンまで、自分に合った講座を見つけられるでしょう。
忍者CODE

忍者CODEは、プログラミング初心者が挫折しないよう工夫されたオンライン学習サービスです。基礎的なコーディングスキルをゲーム感覚で習得できるカリキュラムが特長で、問題集形式のレッスンを解き進めながら楽しんで学べます。直接的に生成AI専門の講座があるわけではありませんが、AI入門記事やチュートリアルも提供されており、Pythonで簡単なAIを作る方法など初心者向けのコンテンツも扱っています。
忍者CODE最大の魅力は、手厚いサポート体制による挫折率の低さです。わからない点はメンターにすぐ相談でき、受講生同士が切磋琢磨できるコミュニティも整備されています。誰もが最初につまずくポイントを押さえた教材設計になっているため、「プログラミングの勉強は初めて」という人でも着実にスキルアップ可能です。まずはプログラミングの基礎素養を身につけ、その延長でAIにも挑戦したいというステップには最適な環境と言えるでしょう。
料金設定も比較的リーズナブルで、月額制やコース制など柔軟なプランがあります(詳細は要問い合わせ)。本格的なAI開発に入る前に、ITリテラシーやコードを書く力を養いたい方に向いています。忍者CODEで土台を作り、その後より専門的なAIスクールにステップアップするといった学習ルートも有効でしょう。
AI CONNECT
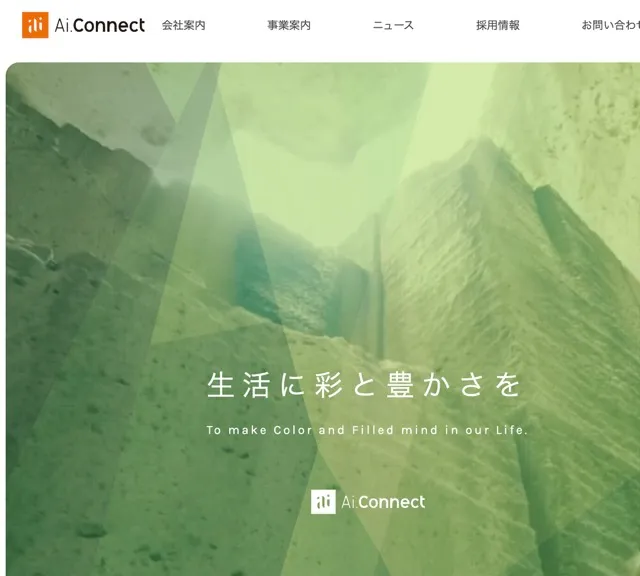
AI CONNECTは、リスキリング補助金制度と連携しており、実質的に自己負担なしで受講できる生成AIスクールです。提供される全14種類のコースでは、データ分析の基礎から、先進的な生成AI技術の応用まで、幅広いスキルを習得できます。
また、AI CONNECTは1万件以上の求人情報を有するデータベースを活用し、学習と並行してキャリア形成を強力にサポート。個別のキャリアカウンセリング、企業紹介、履歴書・職務経歴書の作成支援、面接対策まで、就職や転職活動を総合的にバックアップする体制が整っています。
生成AIスキルが活かせる主な職業・副業
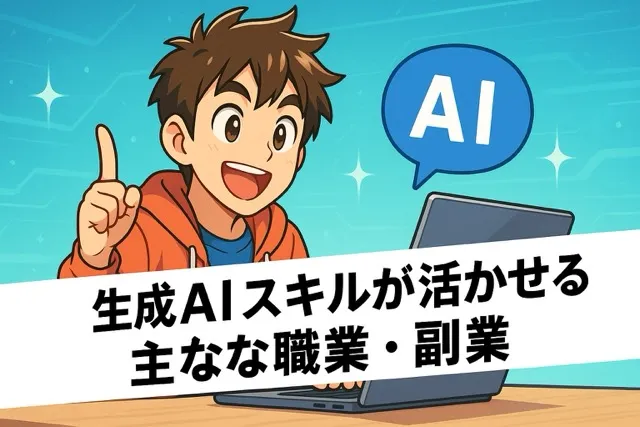
プロンプトエンジニア|社内自動化支援
プロンプトエンジニアとは、AIに与える指示文(プロンプト)を工夫し、望むアウトプットを引き出す専門家のことです。生成AIブームに伴い登場した新しい職種で、社内の業務自動化支援などに活用されています。例えば、社内データから自動でレポートを作成したり、チャットボットを調整して社員からの問い合わせ対応を自動化したりする際に、プロンプトエンジニアがその威力を発揮します。
この職種では、社内の様々な部署と連携しながら、業務フローの中にAIを組み込む役割を担います。具体的には、「どのような指示をAIに与えれば望む結果が得られるか」を試行錯誤し、最適なプロンプトを設計します。
 編集長
編集長プログラミングの知識が求められるケースもありますが、必須というわけではなく、言葉のセンスや発想力が物を言う場面も多いです。
まだ新しい職域であるため、ノウハウを持つ人が少なく、早めにスキルを身につけておけば企業内で重宝される存在となるでしょう。
AIチャットボット運用・カスタマーサポート
AIチャットボット運用は、顧客対応にAIを活用する分野です。顧客からの問い合わせに24時間自動応答するチャットボットは、多くの企業で導入が進んでいますが、そのシナリオ設計や回答精度のチューニングを行うのがこの仕事です。生成AIを組み込んだ高度なチャットボットであれば、プロンプトの工夫次第で人間に近い自然な応答を返すことができます。
具体的な業務としては、チャットボットに組み込むQ&Aデータの整備、AIモデルへの継続的な学習データ投入、応答ログの分析と改善などがあります。カスタマーサポートの現場をよく理解しつつ、AIの特性も踏まえて調整を行う必要があるため、両方の知識が求められます。生成AIスクールで学んだプロンプト設計力や、会話データの扱い方などが役立つでしょう。
近年では「チャットボット担当」といった形で企業内にポジションが設けられるケースも増えてきました。顧客満足度を左右する重要な役割であり、AIスキルとカスタマーサービススキルの両方を活かして活躍できるでしょう。
AIライター/編集|記事生成・リライト
コンテンツ制作の分野でも生成AIスキルは活躍します。AIライター/編集者は、AIを活用して記事やコピーを効率的に作成・編集する職種です。具体的には、ブログ記事の下書きをAIで生成してから人間が仕上げたり、既存の記事をAIでリライトして読みやすくしたりする業務が考えられます。
従来、1本の記事を書くのに数時間かかっていたものが、AIの力を借りれば下書き作成は数分で完了します。その分、人間はファクトチェックや文章のトーン調整、付加価値となる部分の執筆に注力できます。AI編集者は、AIが出力した文章のクセや弱点を理解し、より自然で正確な文章に磨き上げるスキルが求められます。
副業としても人気で、Webライターが生成AIを使って執筆本数を増やしたり、新人ライターの教育にAI添削を活用したりといった事例もあります。生成AIスクールで学んだ文章生成のテクニックやプロンプト工夫は、まさにこの領域で直接的に役立つでしょう。
マーケター|広告文作成・LP改善・分析
マーケターにとっても生成AIスキルは強力な武器になります。広告コピーの作成、ランディングページ(LP)の文言改善、データ分析レポートの自動生成など、マーケティング業務の様々な場面でAIが活用可能です。例えば、新商品のキャッチコピーを考える際、AIに数十パターンの案を出させてその中からインスピレーションを得る、といった使い方ができます。
また、A/Bテスト用にLPの文章やデザインパターンを複数AIで生成しておき、効果検証するといったスピード感ある施策も可能です。データ分析の分野では、スプレッドシートの数値を読み込ませて「〇〇という傾向があります」とAIに要約させることで、レポート作成の手間を削減するといったことも行われています。
マーケター自身が生成AIを使いこなせれば、コンテンツ制作から分析まで一気通貫で進められるため、業務効率と成果の両面でメリットがあります。生成AIスクールで学んだプロンプトスキルやデータ処理の知識は、こうしたマーケティング現場で即戦力となるでしょう。「AIも使いこなせるマーケター」は企業からの需要も高まっており、自身の市場価値向上にもつながります。
ノーコード自動化(Zapier/Make活用)
プログラミング不要でツール間の連携を実現できるノーコード自動化ツール(ZapierやMakeなど)は、生成AIとの相性も抜群です。これらを駆使する自動化スペシャリストは、社内の様々な業務プロセスを効率化する役割を担います。例えば、フォームに入力された顧客問い合わせ内容をZapierで受け取り、GPT-3に要約させてSlackに通知する、といった一連の流れをコードを書かずに構築できます。
ノーコードツールを使えば、エンジニアでなくとも高度な自動化が可能です。生成AIスクールで学んだAPIの扱い方やワークフロー設計の考え方は、こうしたツール運用に応用できます。特に中小企業や非IT部門ではエンジニアリソースが限られているため、ノーコード&AIで業務改善できる人材は重宝されます。
副業としても、個人で企業の自動化コンサルティングを請け負うケースが増えています。「営業活動の一部をAIで自動化したい」といったニーズに対し、ノーコードツールでサッと仕組みを作れるスキルは大きな強みです。
 編集長
編集長プログラミングが苦手でもツール活用で十分戦えるため、文系出身者にも狙い目の領域と言えるでしょう。
画像生成クリエイター|サムネ・素材販売
画像生成クリエイターは、MidjourneyやStable Diffusionといった画像生成AIを使ってクリエイティブなビジュアルを制作する仕事です。YouTube動画のサムネイル画像やブログ記事のアイキャッチ、SNS広告用のイラストなど、用途に応じたオリジナル画像を短時間で作り出せるため、デザイナーやコンテンツ制作者から注目されています。
例えば、従来はデザイナーに依頼して数日かかっていたサムネイル作成が、生成AIを使えば自分でイメージを指示して数分で候補画像を得られます。その中から良いものを選び、細部を微調整して完成させることで制作コストと時間を大幅に削減できます。また、生成した画像素材をストックフォトサイトで販売するといった副業も可能です。
画像生成AIの品質は年々向上しており、それを扱える人材への需要も増えています。生成AIスクールで学んだ高品質なプロンプトの作成方法や、生成画像を編集・加工するテクニックは、この分野で大いに役立つでしょう。デザインの専門知識がなくても、AIツールを活用することでクリエイターとして活躍できるチャンスが広がっています。
動画生成・編集|広告/YouTube向け
動画の世界でも生成AIは革新をもたらしています。動画生成・編集の分野では、AIを使って動画コンテンツを自動生成したり、編集作業を効率化したりする動きが活発です。例えば、AIによる自動ナレーション生成や、顔写真から合成音声付きのプレゼン動画を作るサービスなどが登場しており、広告動画やYouTubeコンテンツ制作のハードルが下がっています。
また、動画編集では、長尺動画からAIが重要シーンを抜き出してショートクリップを作成したり、カット割りやテロップ挿入を自動で行ったりといった支援ツールが登場しています。生成AIスキルを持った動画クリエイターであれば、こうした最新ツールを駆使してクオリティと生産性の両立を図ることが可能です。
広告代理店やメディア企業でも、AIを取り入れた動画制作のニーズが高まっています。生成AIスクールで学んだスキルを応用すれば、企画から編集まで一貫してAI活用できる人材として重宝されるでしょう。個人でYouTubeチャンネルを運営している人にとっても、動画生成AIを使いこなすことでコンテンツ量産や編集時間短縮といった恩恵が得られます。
データアナリスト|AIでの分析・レポート
企業が保有する膨大なデータを分析しビジネスに活かすデータアナリストの仕事にも、生成AIは力を発揮します。具体的には、データのパターンや傾向をAIに自動で読み取らせてレポートを作成したり、プレゼン資料の文言をAIに下書きさせたりといったことが可能です。Excelの表をPasteするだけで「売上が先月比10%増加しています」などの文章を生成してくれるAIツールも登場しており、分析結果の共有が格段に効率化されます。
従来、分析業務では数値の解釈やレポート作成に多くの時間が割かれていましたが、生成AIを活用すればその部分を自動化・アシストできます。アナリストはより本質的な考察や戦略提案に集中できるため、アウトプットの質向上にもつながります。もちろんAIの分析結果を鵜呑みにせず、人間が検証・補足することは必要ですが、ツールとして使いこなせれば非常に強力です。
生成AIスクールで学んだデータ処理や要約のスキルは、このような半自動レポート作成業務で大いに役立つでしょう。数理的な専門知識に加えてAI活用の知見も備えたデータアナリストは、今後ますます需要が高まると予想されます。
アプリ開発者|AI機能実装・連携
ソフトウェア開発の現場でも、生成AIスキルを持ったアプリ開発者が求められています。Webアプリやモバイルアプリに、ChatGPTのような対話AI機能や画像生成機能を組み込むケースが増えており、その実装やチューニングができるエンジニアは貴重です。たとえば、カスタマーサポート用のチャット機能に生成AIを統合したり、ユーザーがアップロードした写真をAIで自動補正する機能を開発したりと、アイデア次第で様々な応用が考えられます。
こうした開発には、従来のプログラミングスキルに加えて、AIモデルのAPI利用やデータ処理の知識が必要です。生成AIスクールで学んだPythonコーディングやAPI連携のノウハウは、まさに実践の場で武器となるでしょう。また、AIならではの考慮点(応答にムラがある、誤情報を返す可能性がある等)を理解して開発に反映できる点でも、専門知識を持つエンジニアは重宝されます。
現在、ほとんどのアプリケーションが何らかの形でAIとの連携を検討し始めており、「AIも使える開発者」は引く手あまたの状況です。既にエンジニアの方が生成AIスクールでスキルアップするケースも多く、キャリアの選択肢を広げる意味でもAI開発スキルを身につけておく価値は高いでしょう。
社内研修講師|AI活用トレーナー
AI時代の到来に伴い、社内研修講師として社員にAIツールの使い方を教えるポジションも現れています。生成AIを活用した業務効率化術や、社員一人ひとりが知っておくべきAIリテラシーについて研修するAI活用トレーナー的な役割です。例えば、新入社員向けに「ビジネスでChatGPTを使う際の注意点」や「文章生成AIで企画書を作成するコツ」といった講座を開催するイメージです。
この職種では、自らがAIツールを使いこなせることはもちろん、人に分かりやすく教えるスキルも必要です。生成AIスクールで体系立てて学んだ知識は、そのまま研修教材を作成する際のベースになります。具体例を交えながらAIの可能性と限界を伝え、受講者が実践できるようサポートすることで、組織全体のAI活用レベルを底上げする役割を果たします。
まだ専任担当者を置く企業は限られていますが、今後AI活用が一般化するにつれて需要が高まるでしょう。副業的にセミナー講師として各社を回るスタイルも考えられます。AIに精通し、人前で話すのが得意な方にとっては、新たなキャリアの一つとして検討する価値があります。
翻訳・ローカライズ|多言語展開
生成AIの言語能力を活かし、翻訳・ローカライズの現場でも活用が進んでいます。従来、人間が行っていた文章の翻訳作業をAIが下訳し、それを翻訳者がチェック・修正するポストエディットという形が一般化しつつあります。生成AIを使えば、かなり自然な翻訳文が瞬時に得られるため、翻訳者はニュアンスの微調整や専門用語の統一といった高度な部分に集中できます。
また、ローカライズでは単に言語を訳すだけでなく、文化的な調整やクリエイティブ要素の翻案も求められます。例えば広告コピーを他言語向けにローカライズする際、AIがいくつか提案した表現の中から適切なものを選び、人間がブラッシュアップする、といった協業が行われます。生成AIスクールで学んだ高度なプロンプトテクニックは、AIにより良い翻訳をさせるための指示出しに役立つでしょう。
現在、翻訳業界ではAIを使いこなせる人とそうでない人で生産性に大きな差が生まれています。生成AIスキルを身につけた翻訳者・ローカライズ担当者であれば、短時間で多くの案件をこなすことが可能となり、収入アップにも直直します。
日本では英語の壁もあり多言語展開に苦労する企業が少なくありませんが、生成AIを補助輪にすることで大幅に効率化できます。言語や文化の専門知識にAIのパワーを組み合わせられる人材は、今後さらに重宝されるでしょう。
AIコンサル|業務設計とPoC伴走
最後に紹介するのは、AIコンサルタントです。これは企業の業務課題に対し、どのようにAIを導入すれば解決できるかを提案し、実証実験(PoC)の伴走まで行う仕事です。コンサルティングファームだけでなく、フリーのコンサルタントとして活動する人も増えてきました。生成AIの登場により、「自社業務に取り入れたいが何から手を付ければいいかわからない」という企業が多く、そうした企業に対して適切なアドバイスができる人材は非常に重宝されています。
業務ヒアリングを行い、生成AIで自動化できそうなプロセスを見極め、小規模なPoCを実施して効果検証し、本格導入へとつなげる――こうした一連の流れをリードするのがAIコンサルの役割です。必要に応じて外部のAI開発パートナーと連携しつつ、企業側のプロジェクトマネージャー的な立場を取ることもあります。
生成AIスクールで得た知識はもちろん、業界動向や多数のAIツールに関する情報も総動員して提案を行うため、勉強量は要求されますが、その分ビジネスインパクトの大きい仕事です。
 編集長
編集長経験を積めば独立してコンサル業を営むことも可能で、まさにこれからの時代に求められるプロフェッショナルと言えるでしょう。
生成AIスクールに関するよくある質問
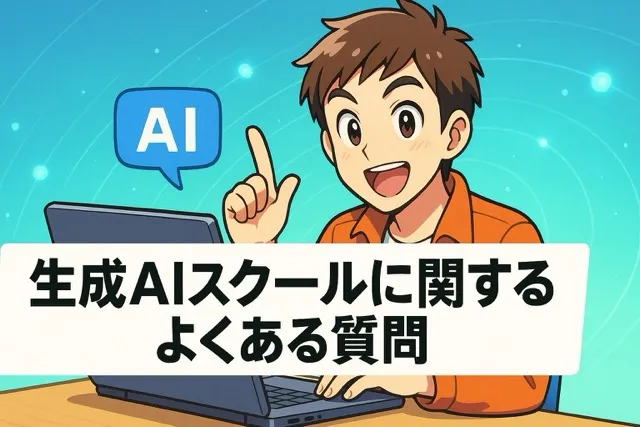
未経験からでもついていけますか?
はい、未経験からでも問題なく受講できます。ほとんどの生成AIスクールは、AI初心者やプログラミング未経験者を対象にカリキュラムを構成しています。基礎的な概念や専門用語の解説から始まり、徐々にステップアップしていくため、前提知識がなくても心配はいりません。実際に、文系出身の社会人や主婦の方など、IT未経験の受講生も多数修了し成果を上げています。
もちろん、独学と比べればサポートがある分、困ったときは質問できる環境が整っています。それでも不安な場合は、入門セミナーや体験会に参加してみると良いでしょう。スクールの雰囲気や難易度を事前に掴むことで、「これなら自分でもできそうだ」と安心してから本講座に臨めます。
重要なのは、未経験だからといって臆せずチャレンジすることです。カリキュラムをこなし、課題に取り組んでいけば、着実にスキルは身についていきます。わからない部分があっても、サポートを活用しながら一つ一つ解決していけば大丈夫です。未経験からスタートした先輩受講生のレビューなども参考に、自信を持って飛び込んでみてください。
費用相場はいくら?最安はどこ?
生成AIスクールの受講料は、相場としておよそ10万~30万円前後が一つの目安です。ただし、提供内容によって大きく異なります。マンツーマン指導や転職支援が手厚いスクールでは50万円以上となるケースもありますし、逆に動画教材中心のセルフラーニング型であれば10万円を切ることもあります。
最安値という観点では、例えば先ほど紹介したデイトラの生成AIコースは約10万円弱と低価格です。また、TechAcademyの短期コースも15万円程度から始められます。さらに、補助金・給付金を活用できるスクールであれば自己負担額を大きく減らせます。例えばRUNTEQは給付金適用で実質11万円程度、DMM 生成AI CAMPも7割引き相当の負担で受講可能です。
一方で、「安ければ良い」というものでもありません。重要なのは内容とのバランスです。少々高額でもサポートが充実して短期間で成果が出せるなら費用対効果は高いですし、逆に安くても挫折してしまってはお金が無駄になってしまいます。各スクールの特徴と自分の予算感を照らし合わせ、総合的に判断すると良いでしょう。
学習期間はどれくらい必要?
スクールやコースによって学習期間はまちまちですが、平均的には2~3ヶ月程度のプログラムが多い印象です。短期集中型なら1~2ヶ月で完結するものもありますし、逆にじっくり学ぶ長期コースでは6ヶ月~1年に及ぶこともあります。例えば、TechAcademyは最短4週間から選べ、Aidemyは3ヶ月プラン、RUNTEQなら9ヶ月といった具合です。
最適な学習期間はあなたの目標と生活スタイルによります。忙しい社会人であれば無理のないペースで3ヶ月程度、早く結果を出したい場合は1~2ヶ月で短期集中、といった選び方が考えられます。また、受講期間中だけでなく修了後も自主的に学習を継続することが大切です。生成AIの分野は日進月歩ですので、スクール終了後も新しい情報をキャッチアップし続けることで、スキルを陳腐化させずに済みます。
ですので、「〇ヶ月学べば完璧」といったゴールはあまり意識せず、まずは一区切り○ヶ月学んで基礎を固め、その後も自走できるようになることを目指しましょう。スクールはあくまで土台作りと考え、期間終了後にどれだけ自分で積み上げられるかが、本当の実力につながります。
オンラインと通学どっちが良い?
一長一短があり、あなたの状況によります。オンラインと通学(オフライン)それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルや学習スタイルに合った方を選びましょう。オンラインの良い点は、場所に縛られず自宅からでも受講できる手軽さと、時間の柔軟性です。録画講義が提供されるスクールなら好きな時間に視聴できますし、移動時間もゼロなので忙しい人に向いています。
一方、通学のメリットは対面ならではの臨場感や強制力です。決まった時間に教室へ行くことでサボりにくく、直接講師に質問できる安心感もあります。また、オフラインでは受講生同士の交流が生まれやすく、その場でディスカッションしたり情報交換できる利点があります。ただし教室が近くにないと通えない点、スケジュールを空ける必要がある点は制約となります。
現在では、多くのスクールがオンライン対応ですが、中にはハイブリッド型(基本オンライン+任意の対面イベント)を採用する所もあります。迷ったらまずオンラインで始め、物足りなければオフライン講座や勉強会に参加してみるのも一手です。どちらが「良い・悪い」というより、自分が続けやすい方を選ぶことが結果的に成功への近道となるでしょう。
PCスペックはどの程度必要?
基本的には一般的なパソコンが1台あれば十分です。多くの生成AIスクールでは、ブラウザ上で動作するAIツール(ChatGPTなど)やクラウドサービスを利用するため、高性能なマシンは必須ではありません。例えば、Chromeなど最新ブラウザが快適に動く程度のPC(ここ5年以内に発売されたCore i5相当のCPU・メモリ8GB以上)であれば問題なく受講できるでしょう。
ただし、画像生成AIをローカルで動かす、機械学習モデルを自分で訓練する、といった高度なことに挑戦する場合は、高性能GPUを搭載したPCや16GB以上のメモリがあった方が望ましいです。しかし、そのような専門的な研修は一部で、通常はクラウド上の環境をスクール側が用意してくれるため、自宅PCのスペックを気にする必要はあまりありません。
強いて言えば、安定したインターネット回線が重要です。オンライン講義やクラウドサービス利用時にネットが不安定だと支障が出ますので、有線接続や高速Wi-Fiを準備すると安心です。まとめると、最新のゲームを動かすようなハイスペックPCは不要ですが、ネット環境だけは整えておきましょう。
無料体験や返金保証はありますか?
多くのスクールで無料体験・説明会が用意されていますが、返金保証の有無はスクール次第です。まず、無料体験に関しては、オンライン説明会や1週間程度の体験コースを実施しているところが目立ちます。例えば、SHIFT AIは無料セミナーを常時開催していますし、TechAcademyもコースによっては1週間の無料体験期間を設けています。申し込み前にスクールの雰囲気や講義スタイルを知る良い機会なので、積極的に利用しましょう。
一方、返金保証については、「○日以内なら全額返金」といった制度を設けているスクールも一部あります。ただし全てではなく、規約に細かな条件が定められている場合もあるため、事前に確認が必要です。特に高額なスクールでは返金対応がシビアなことも多いので、本当に納得してから申し込むことが大切です。
不安な場合は、受講開始後のフォローについても問い合わせてみると良いでしょう。「もし合わなかったらどうなりますか?」と聞けば、休会制度や別コースへの振替など代替案を教えてくれるかもしれません。信頼できるスクールであれば、受講生の満足を第一に考えて柔軟に対応してくれるはずです。
給付金・補助金の対象になりますか?
スクールや講座によりますが、対象となる場合があります。社会人の学び直し支援として、国の給付金や自治体の補助金が利用できる講座がいくつか存在します。例えば、経済産業省のリスキリング補助金や、厚生労働省の専門実践教育訓練給付金に指定されているスクールでは、受講料の50~70%相当が支給されます。
具体的には、Aidemy PremiumやRUNTEQ、DMM 生成AI CAMPなどが給付金の対象として知られています。これらのコースでは、申し込み前にハローワークでの手続きが必要だったり、一定の受講期間が設けられていたりと条件がありますが、その分修了後に大きな経済的メリットがあります。高額なスクールほど給付金適用時の恩恵も大きくなるため、該当する場合は是非活用したいところです。
なお、補助金対象かどうかは各スクールの公式サイトに明記されていることが多いです。「一般教育訓練給付制度対象講座」といった記載があるか確認し、不明な場合は問い合わせてみましょう。制度を上手に使えば自己負担を大幅に軽減できますので、特に費用面が心配な方はチェックしてみてください。
課題やポートフォリオは作れますか?
はい、多くのスクールで成果物を作れるカリキュラムが組まれています。単に知識をインプットするだけではなく、実際に手を動かして課題に取り組み、最終的にポートフォリオとなるアウトプットを作成する流れが一般的です。例えば、記事生成系のコースであればAIを使って実際にブログ記事を何本か執筆したり、開発系のコースであれば簡易なAIチャットボットやWebアプリを構築したりします。
こうして作成した成果物は、就職・転職活動や副業案件獲得時に強力なアピール材料となります。「自分はこれだけのものを作れます」と示せるので、未経験分野への挑戦でも説得力が増します。スクールによっては、最終課題として自由課題プロジェクトが設定されており、受講生各自が工夫を凝らしたAIアプリや資料を制作し、講師からフィードバックをもらえる仕組みもあります。
学んだ知識を形に残すことで理解も深まりますし、自信にもつながります。ぜひ積極的に課題制作に取り組み、オリジナルのポートフォリオを作り上げてください。努力して作った作品は、きっと今後のキャリアにおいて大きな武器となるはずです。
途中解約・休会は可能ですか?
スクールによって対応は様々ですが、契約時の規約次第で途中解約や休会も可能な場合があります。月額課金制のスクール(例:ホリエモンAIスクール)であれば、翌月以降の支払いを止めれば実質的に途中解約ができます。ただし入学金など初期費用の返金は基本的に無い点に注意が必要です。
一括払いのスクールでは、一定期間内(例:14日以内)であれば返金保証付きというケースもありますが、期間経過後は原則返金不可となることが多いです。どうしても継続が難しくなった場合は、速やかにスクール事務局へ相談しましょう。場合によっては、休会扱いとして受講期間を延長してもらえたり、次の開講回に振替してもらえたりする可能性があります。
契約前に利用規約の解約条件をよく読み、納得した上で申し込むことが大切です。特に長期コースの場合、仕事や家庭の事情で計画通り進められないリスクもゼロではありません。そうした場合のオプションが用意されているスクールだと、安心感が違います。疑問点は事前に問い合わせ、後悔のないようにしましょう。
他のプログラミングスクールとの違いは?
生成AIスクールと一般的なプログラミングスクールでは、学ぶ内容や目的に違いがあります。プログラミングスクールはWeb開発やアプリ開発など「コードを書く力」を身につけるのが主眼ですが、生成AIスクールはAIツールの使い方やプロンプト設計など「AIを活用する力」にフォーカスしている点が大きな違いです。
言い換えれば、従来のプログラミングスクールはゼロからシステムを構築するスキルを教えるのに対し、生成AIスクールは既存のAIサービスを活用して効率化・自動化するスキルを教えると言えます。もちろん、一部内容が重なることもあり、プログラミングスクールでもAI概論を扱ったり、逆にAIスクールでも簡単なPythonコーディングを教えたりする場合もあります。
要は、自分が「AIを使う人」になりたいのか「AIを作る人」になりたいのかで選択肢が変わります。コードを書くことより業務活用アイデアに興味があるなら生成AIスクールを、AIそのものを開発したいならプログラミングスクール(もしくはAI開発特化のスクール)を選ぶと良いでしょう。最近では両者のハイブリッド型も登場しているため、カリキュラムをよく比較して自分の目標にフィットする方を選んでください。
生成AIスクールおすすめランキングまとめ
生成AIスクールについて、その選び方からおすすめの講座、活かせるキャリアまでご紹介しました。どのスクールにもそれぞれ強みがあり、あなたの目的や予算に合ったベストな選択肢がきっと見つかるはずです。今は生成AI人材が不足しているブルーオーシャンの状態ですので、スキルを身につけるなら早いほど有利です。
ぜひ本記事を参考に、自分に合ったスクールで学びをスタートしてください。無料説明会や体験講座を活用し、不安や疑問を解消してから本格的に取り組めば、途中で失敗するリスクも減らせます。
 編集長
編集長生成AIスキルを武器に、新たなキャリアや副業の扉を開きましょう。